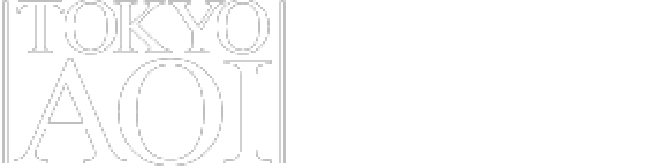TOPICS
トピックス
人事担当者必見!「高年齢者雇用安定法」について重要ポイントを解説
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」といいます。)の経過措置が、令和7年3月31日をもって終了し、継続雇用制度を採用している事業主には、原則として従業員全員についての継続雇用が義務付けられることとなりました。
高年齢者雇用安定法は、高齢者の雇用の安定や再就職の促進等を目的とする法律です。
以下、高年齢者雇用安定法の重要なポイントに絞って解説していきます。
1.60歳未満の定年の禁止
事業主が、雇用している労働者の定年について定める場合、60歳を下回る定年を定めることができなくなります(高年齢者雇用安定法第8条本文)。同条に違反する社内規程等は無効となり、その結果定年の定めがないものとして扱われます(厚生労働省 兵庫労働局 ハローワーク「高年齢者雇用安定法ガイドブック」3頁 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/library/2018131173633.pdf)。なお、単なる慣行として一定年齢で退職することが定着している場合や、選択定年制など早期の退職を優遇する制度における早期の退職年齢は、高年齢者雇用安定法上の「定年」には該当しないものとされます(前掲ガイドブック3頁参照)。
2.65歳までの高年齢者雇用確保措置
(1)必要な措置の種類
次に、事業主が定年年齢を65歳未満と定めている場合、下記①乃至③のいずれかの措置を取ることが義務付けられています(同法第9条第1項)。
①65歳までの定年の引上げ
②65歳までの継続雇用制度の導入
③定年制の廃止
※継続雇用制度とは、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます(同法第9条第1項第2号)。なお、継続雇用制度には、一旦定年で退職の上改めて雇用契約を締結する再雇用制度と定年では退職せずに継続雇用する勤務延長制度があり、再雇用制度とする場合には、1年毎に雇用契約を更新する形態も柔軟に認められています(厚生労働省 確かめよう労働条件「労働条件Q&A」https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/kaiko/q7.html)。
厚生年金保険法の平成12年改正により、老齢厚生年金の支給開始年齢が満60歳から65歳に段階的に引き上げられたことに伴い(男性は平成13年から令和7年度にかけて、女性は平成30年から令和12年とにかけて引き上げが行われる予定です。)、高年齢者雇用安定法の平成16年改正により、老齢厚生年金の支給開始までに収入の空白期間が生じないようにするために、65歳までの雇用確保措置が法的義務へと強化されたことに起因しています。
これらの高年齢者雇用確保措置のうち実際に多く目にするのが、②「65歳までの継続雇用制度の導入」です。③「定年制の廃止」は事実上無期限の雇用契約となりかねないことから導入の抵抗感が強く、また、①「65歳までの定年の引上げ」も人件費や予算との関係で一律で導入することの抵抗感が強いことが理由として挙げられます。
(2)違反時の取扱い
事業主が同法第9条第1項に定める上記義務に違反した場合、厚生労働大臣は、事業主に対して必要な助言及び指導をすることができるとされ(同法第10条第1項)、事業主が助言及び指導をしても違反を継続しているときは高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができ(同条第2項)、事業主が勧告にも従わなかった場合はその旨を公表することができるとされています(同条第3項)。
(3)第9条第1項は事業主に対して私法上の義務を発生させる私法的効力を有する規定か
裁判例の中には、「高年雇用安定法9条に私法的効力のないことは、原判決…のとおりであり、同法の性格・構造・文理・違反の制裁の規定、法改正の経緯及び立法者の意思、並びに私法的効力の違反の効果が不確定であることからして、控訴人ら主張のような解釈は採用することができず…。」と判示するものがあり(大阪高判平21.11.27)、同法第9条第1項について、事業主が労働者を65歳まで継続雇用する等の私法上の義務を発生させる私法的効力を有するかについて、否定的な考え方を示しています。
この場合、事業主に対しては継続雇用の期待的利益(ないし期待権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)が認められ得るにとどまります。
なお、最高裁には、事業主が定めた継続雇用制度を前提として、雇止め法理を類推適用することにより定年後の継続雇用を認めたものがあります(最一小判平24.11.29 津田電気計器事件)。
3.70歳までの就業機会確保の努力義務
高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業確保措置が努力義務として規定されています(同法第10条の2)。本条の定めは2025年4月15日時点では努力措置であるため、基準対象者等については柔軟な設計が可能です(但し、同法の趣旨に反するもの、男女平等に反するもの、公序良俗に反するような定めは認められないものと考えられます。)。
本TOPICSの執筆者:市川雷
※2025年4月22日時点の情報に基づく記事です(参考にされる場合は新法の施行や関連法令の改正等がないかをご確認下さい)。